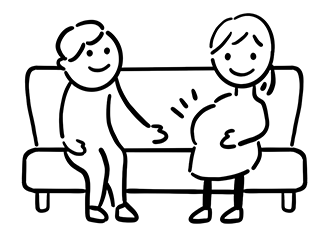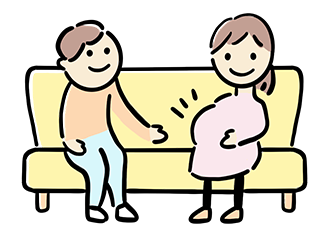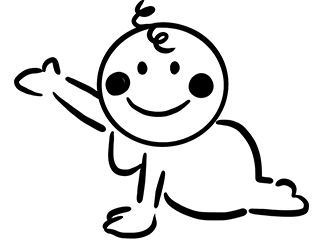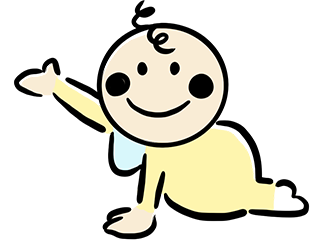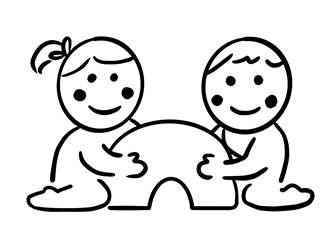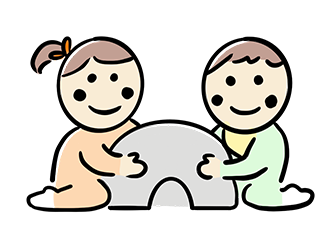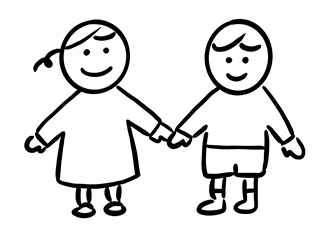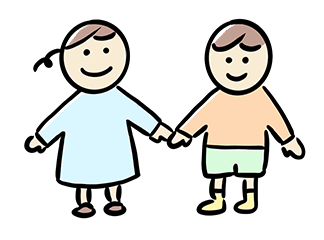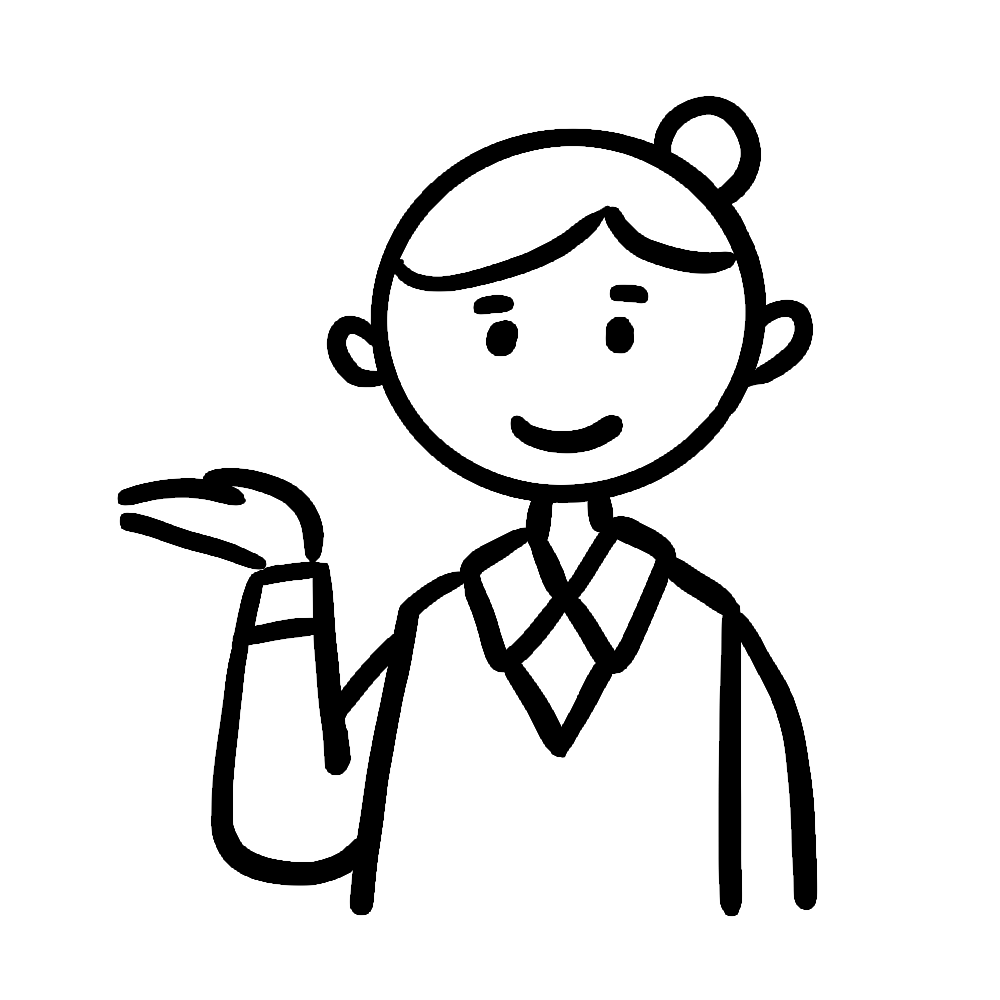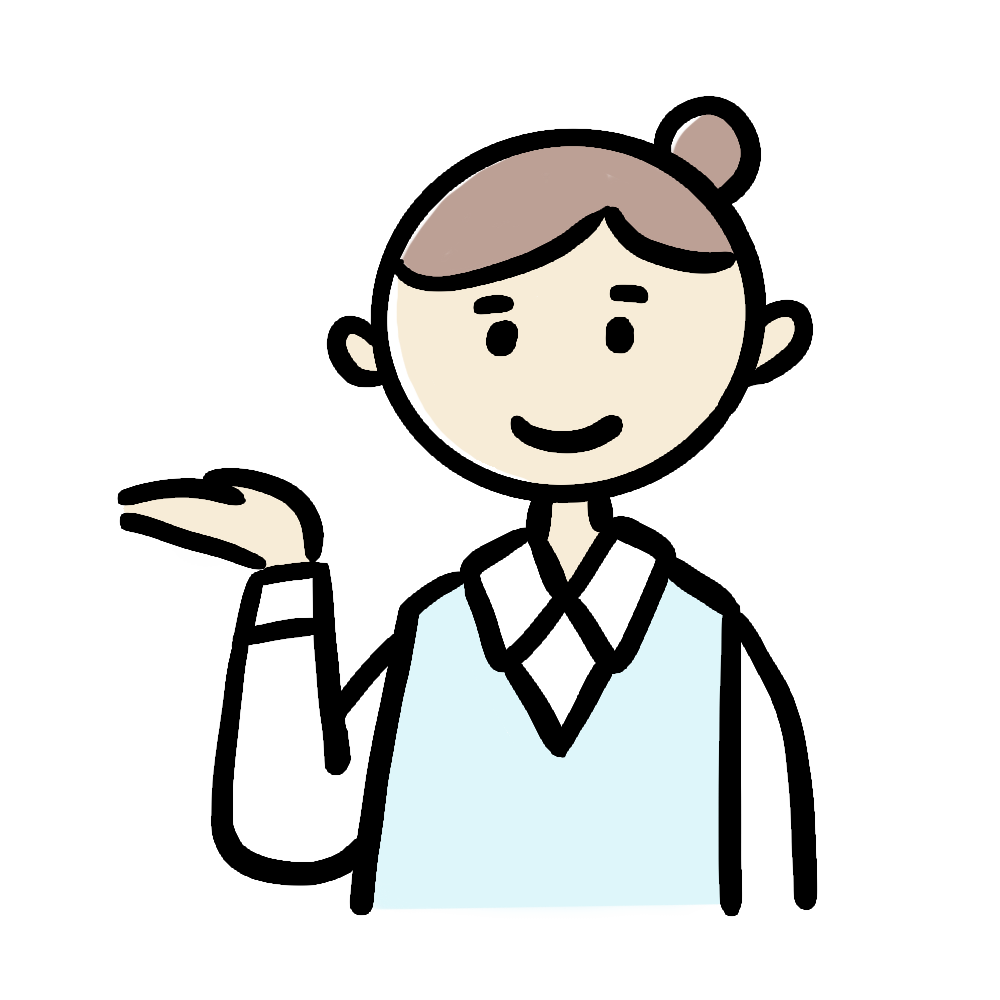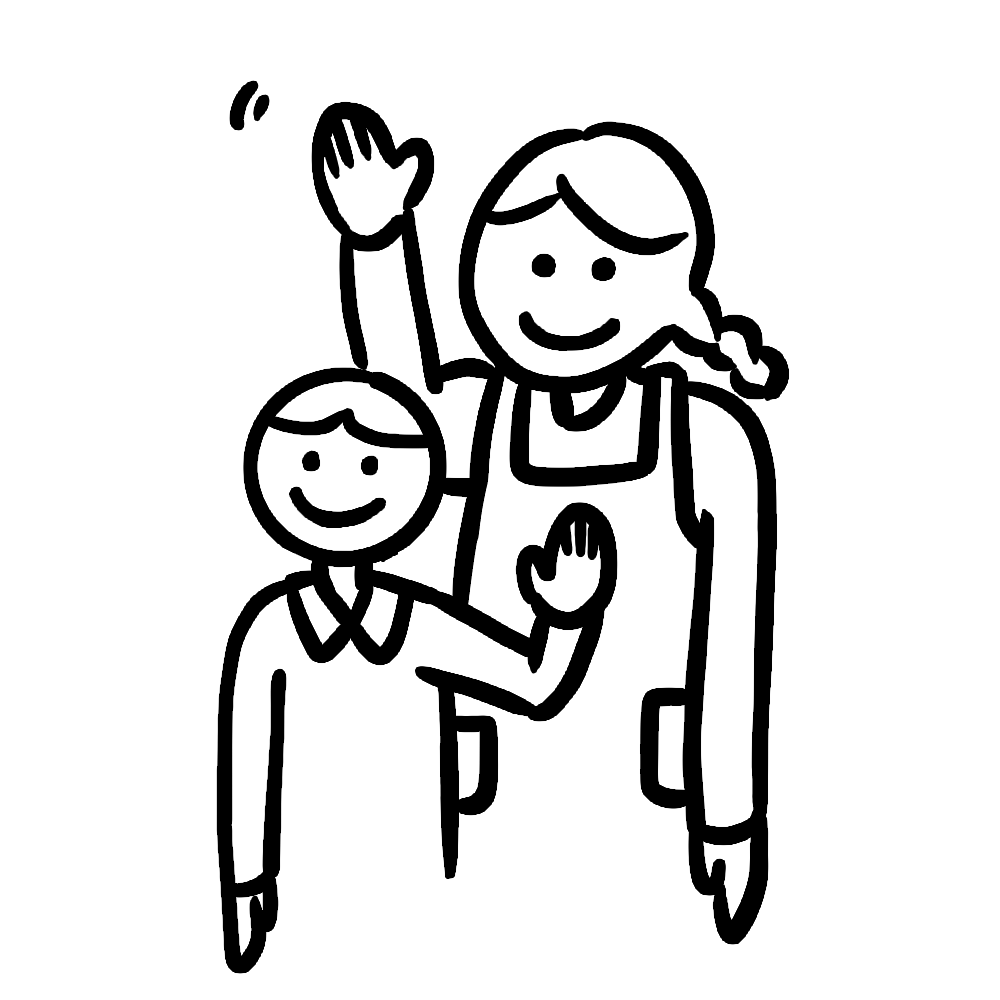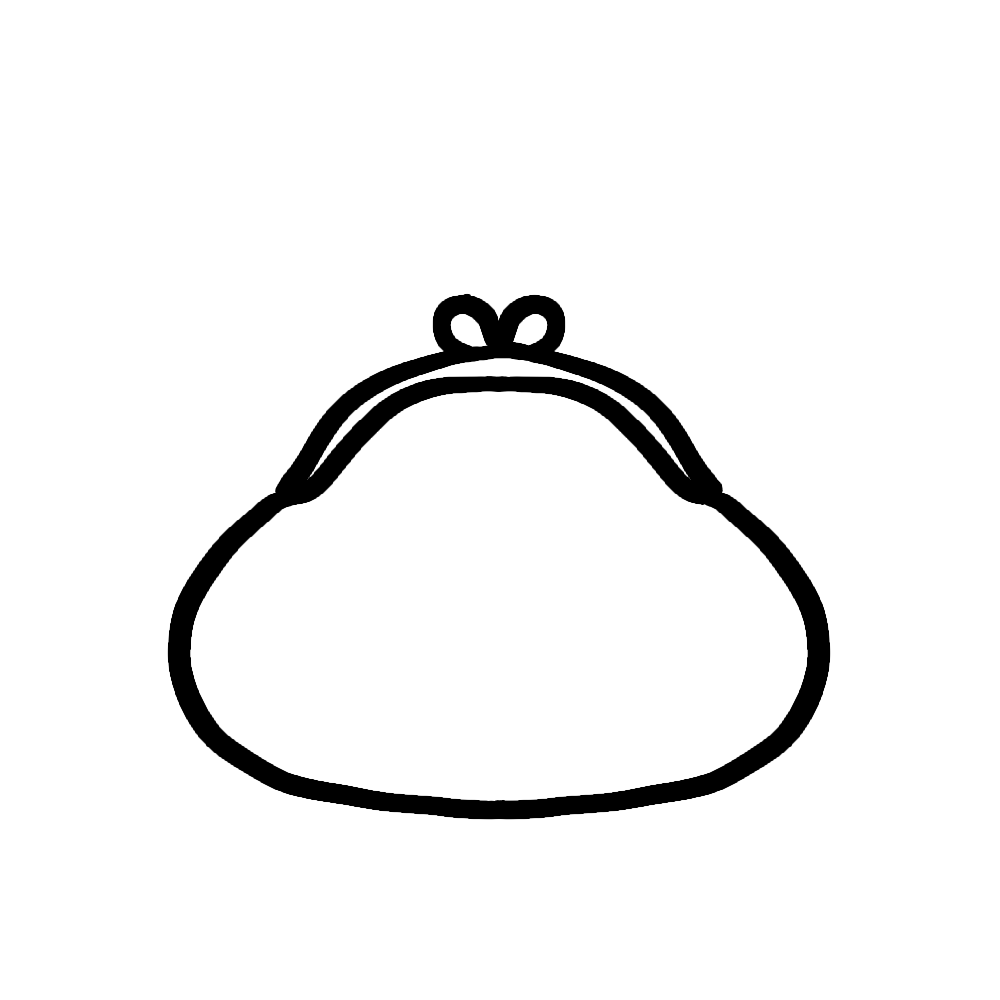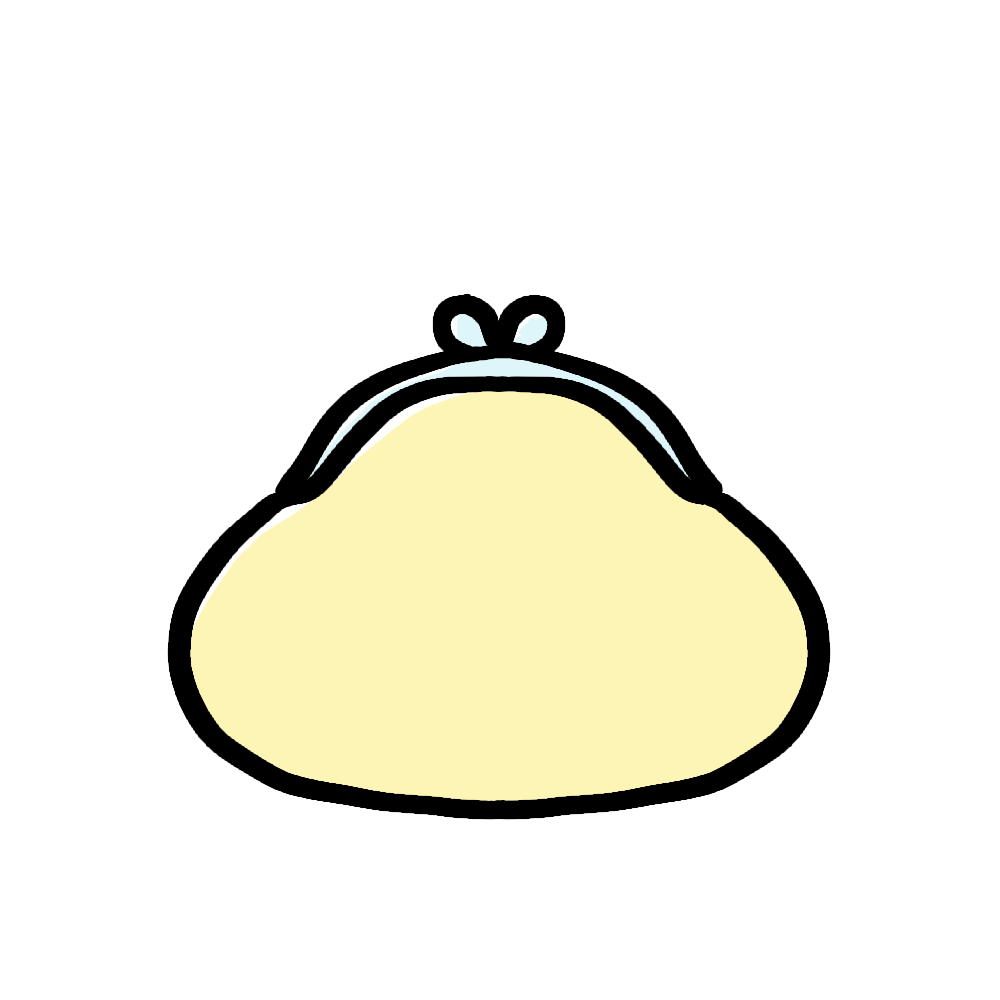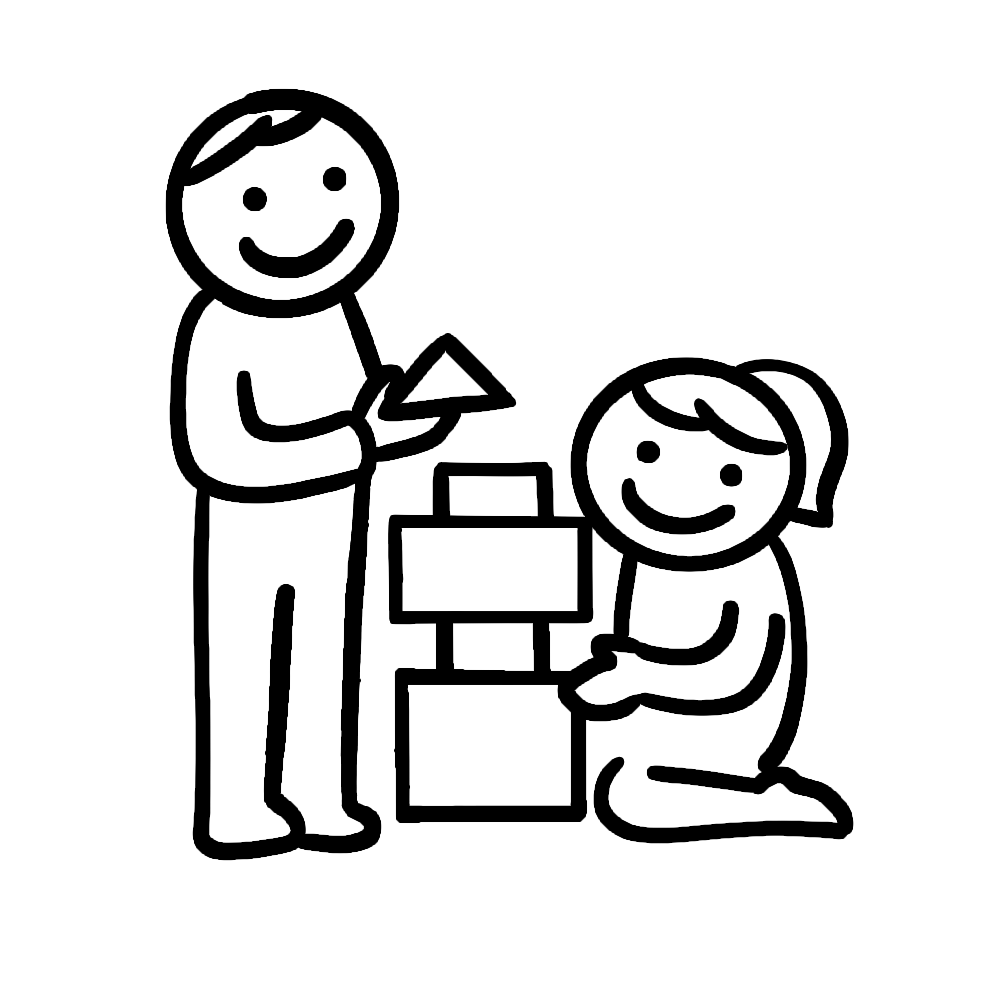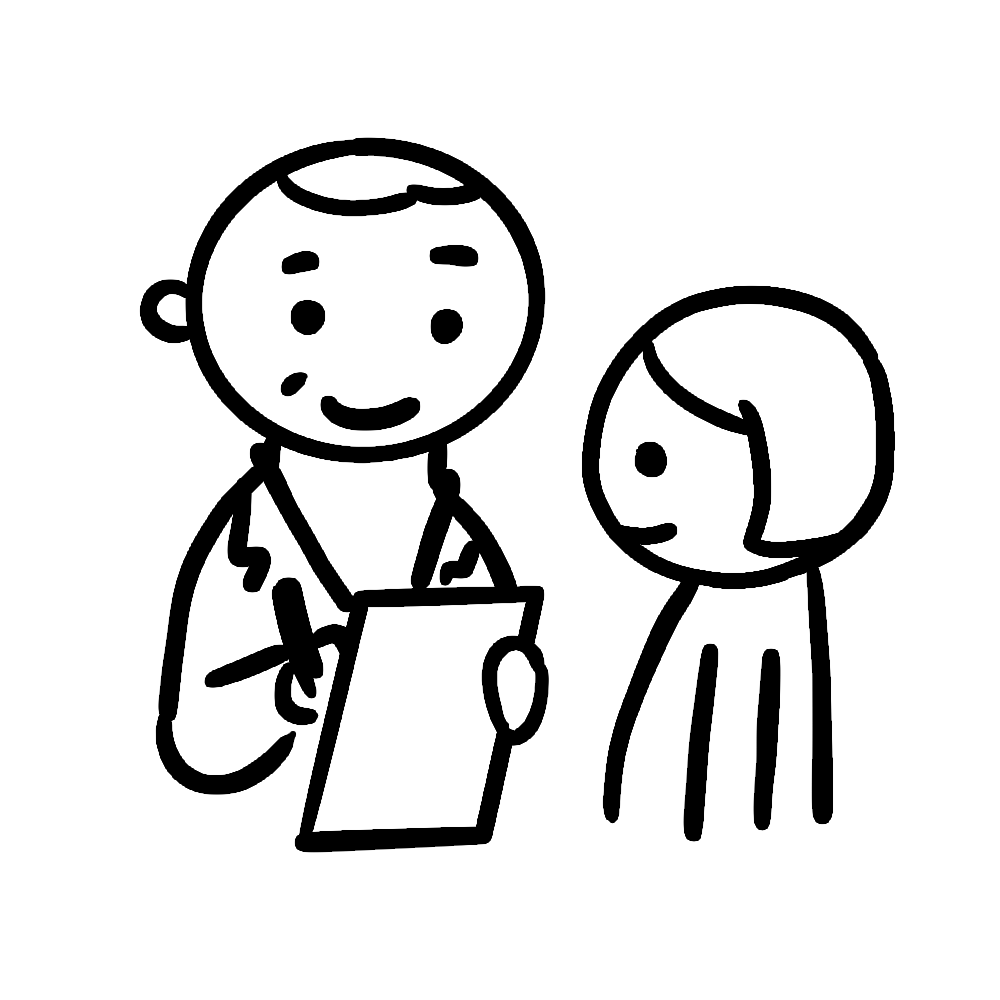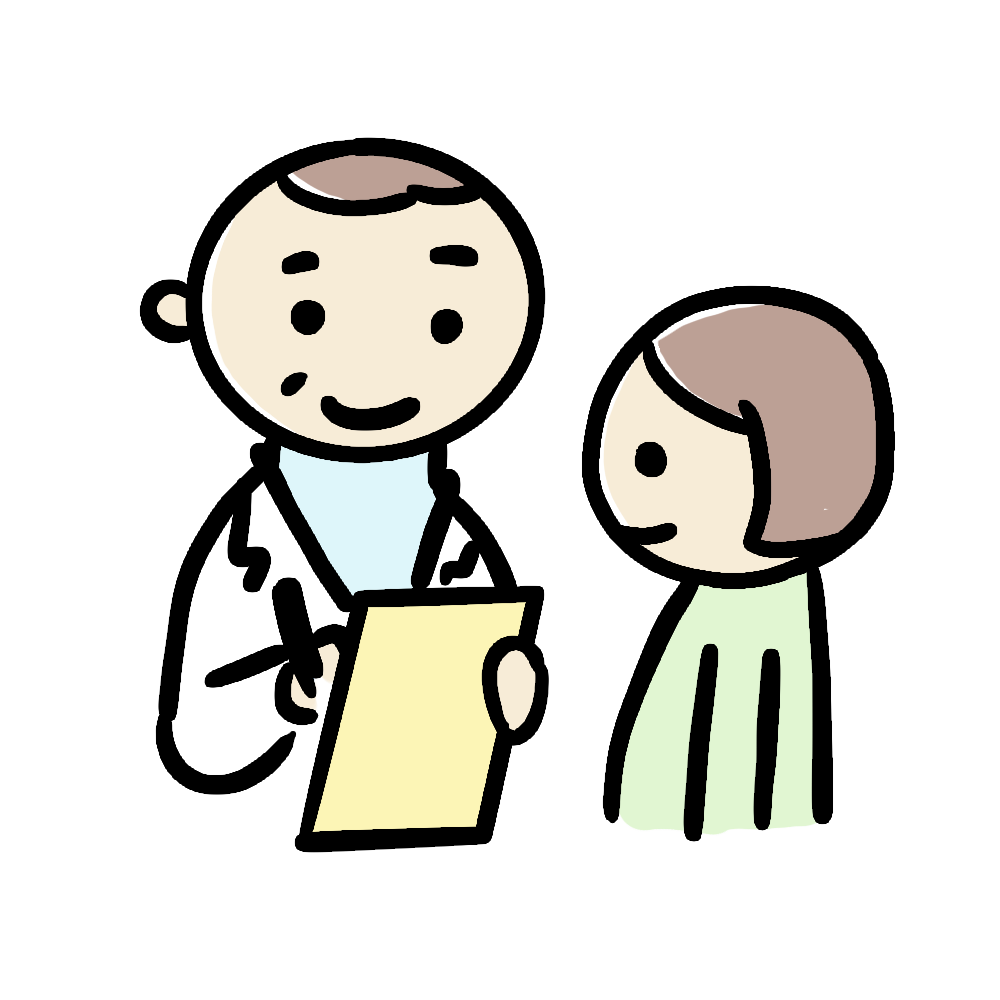お子さまの予防接種について
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2025年7月11日]
- ページ番号:10856
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
枚方市保健所は、令和7年(2025年)7月7日に移転しました。
移転後の住所は下記のとおりです。
〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13-13 (旧保健センター)
(電話番号及びFAX番号に変更はありません)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
予防接種とは
生まれる前は、無菌状態だった赤ちゃんも、生まれるとすぐにいろいろな病気の感染を受けます。
赤ちゃんは、お母さんのお腹にいるときは胎盤を通じて、生まれてからは母乳から免疫をもらっています。
しかし、その免疫も次第にうすれていき、いろいろな病気に対する抵抗力ができあがっていないために感染症にかかりやすくなります。
その感染症から守ってくれるのが予防接種です。病気の原因となるウイルスや細菌の毒性を弱めて作ったワクチンを体内に入れることによって免疫を作り、病気にかからないように、もしかかったとしても軽くすむようにするものなのです。
予防接種のワクチンって何ですか?
感染症の原因となるウイルスや細菌の毒性を弱めたもの、またウイルスや細菌を殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくしてつくった薬液を『ワクチン』といいます。
ワクチンには、その作られる性質から2種類(生ワクチン、不活化ワクチン)に分けられます。
- 生ワクチン
生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)ができます。麻しん風しん混合ワクチン(MR)、麻しんワクチン、風しんワクチン、BCG、おたふくかぜワクチン、水ぼうそうワクチン、ロタウイルスワクチンがこれにあたります。接種後から体内で毒性を弱めた細菌やウイルスの増殖が始まることから、それぞれのワクチンの性質に応じて、発熱や発疹の軽い症状が出ることがあります。十分な抵抗力(免疫)ができるのに約1か月が必要です。 - 不活化ワクチン
細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくしてつくったものです。百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオHib混合(5種混合)ワクチン、百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合(4種混合)ワクチン、ジフテリア、破傷風混合(2種混合)ワクチン、ポリオワクチン、日本脳炎ワクチン、破傷風ワクチン、季節性インフルエンザワクチン、Hib感染症ワクチン、小児の肺炎球菌感染症ワクチン、ヒトパピローマウイルス感染症ワクチンがこれにあたります。この場合、体内で細菌やウイルスは増殖しないため、数回接種することによって抵抗力(免疫)ができます。一定の間隔で2~3回接種し、最小限必要な抵抗力(基礎免疫)ができたあと、約1年後に追加接種をして十分な抵抗力(免疫)ができることになります。しかし、しばらくすると少しずつ抵抗力(免疫)が減ってしまいますので、長期に抵抗力(免疫)を保つためにはそれぞれのワクチンの性質に応じて一定の間隔で追加接種が必要です。
子どもの定期の予防接種一覧
| 定期予防接種 種目 | 対象 ( )内は標準的接種年齢 | 詳細ページ |
|---|---|---|
| ロタ | ロタテック:出生6週0日後から32週0日後まで ロタリックス:出生6週0日後から24週0日後まで (初回接種開始は生後2か月~14週6日後まで ※) | ロタ予防接種について ※0歳児は、月齢が進むと、腸重積症という病気にかかりやすくなります。初回接種は標準的接種年齢の期間内にお受けください。 |
| B型肝炎 | 1歳未満(生後2か月~9か月未満) | B型肝炎の予防接種について |
| 小児肺炎球菌 | 生後2か月以上5歳未満(初回:生後2か月~7か月未満) | 小児肺炎球菌ワクチン接種について |
| 5種混合 | 生後2か月以上7歳6か月未満(初回:生後2か月~7か月未満) | 5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)予防接種について |
| 4種混合 | 生後2か月以上7歳6か月未満(初回:生後2か月~1歳未満) | 4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)予防接種について) |
| ヒブ | 生後2か月以上5歳未満(初回:生後2か月~7か月未満) | ヒブワクチン接種について |
| BCG | 1歳未満(生後5か月~8か月未満) | BCG接種について |
| 麻しん風しん(MR) | 1期:1歳以上2歳未満 2期:5歳以上7歳未満で次年度小学生になる人 | 麻しん・風しん予防接種(MR)第1期・第2期について |
| 水痘 | 1歳以上3歳未満(1回目:1歳~1歳3か月) | 水痘(みずぼうそう)の予防接種について |
| 日本脳炎 | 1期:生後6か月以上7歳6か月未満(初回3歳~4歳) 2期:9歳以上13歳未満(9~10歳) | 日本脳炎予防接種について |
| 2種混合2期 | 11歳以上13歳未満(11歳~12歳未満) | 2種混合(ジフテリア・破傷風)予防接種について |
| HPVワクチン (子宮頸がん予防) | 小学校6年生~高校1年生相当の年齢の女子(中学1年生相当) | HPV(子宮頸がん予防)ワクチンの予防接種について |
他の予防接種との間隔
令和2年10月1日から、他の予防接種との間隔が変更になりました。予防接種後他のワクチンとの間隔をあける必要があるのは、ロタを除く注射生ワクチンです。
他の予防接種との間隔

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
接種場所・申込方法
予防接種を受ける時の注意事項
予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日頃から保護者はお子さんの体質、体温など健康状態によく気を配ってください。そして気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医や枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)に相談してください。
下記のいずれかに該当する人は、予防接種を受けることができません。(接種不適当者)
- 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます。)しているお子さん
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかなお子さん
(注)アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック状態になるような、激しい全身反応のことです。 - BCG接種の場合においては、外傷等によるケロイドが認められるお子さん
- ロタ予防接種については、腸重積症の既往歴のある事が明らかなお子さん、先天性消化管障害を有するお子さん(その治療が完了をしたお子さんを除く)、重症複合免疫不全症(SCID)の所見が認められるお子さん
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態と判断した場合
下記のいずれかに該当する人は医師と相談が必要です。(接種要注意者)
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けているお子さん
(注)あらかじめ主治医と相談し指示に従ってください。 - 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられたお子さんおよび発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さん
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたこお子さん
- 過去に免疫不全の診断がなされているお子さんおよび近親者に先天性免疫不全症の人がいるお子さん
- ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことのあるお子さん
- BCG接種においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのあるお子さん
- ロタ予防接種については、胃腸障害(活動性胃腸疾患、慢性下痢)があるお子さん
予防接種の当日には
予防接種を受ける前に次のことに注意しましょう。
- 当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても体調が悪いと思ったらかかりつけ医に相談の上、接種をするかどうか判断するようにしましょう。
- 受ける予定の予防接種について、必ず「予防接種予診票に添付している説明書」や「予防接種と子どもの健康の冊子」を読んで、予防接種の必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に接種医に質問しましょう。
- 母子健康手帳は必ず持って行きましょう。
- 予診票は、予防接種が接種可能であるかを判定するための重要な資料となりますので正確に漏れのないように記入しましょう。
- 医療機関へは、お子さんの健康状態をよく知っている保護者が連れて行きましょう。
- 予防接種は、お子さんの体調の良いときに受けさせてください。
1か月以内に感染症等にかかった場合や家族や遊び仲間が感染症にかかった場合は、予防接種を受けるまでに一定の期間接種出来ない場合がありますのでこちらを参考にしてください。
予防接種後は、次のことに注意してください。
- 予防接種を受けたあと30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は、はげしい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
よくある質問
Q.予診票つづりがないのですがどうすればいいですか?
A.枚方市で出生届を提出された方や1歳までに転入された方には、予防接種予診票つづりをお渡ししていますが、紛失された場合の再発行や1歳以上で転入された方へのお渡しはしておりません。
予診票は枚方市取扱医療機関にありますので、接種の際に予診票を持っていないことを伝えて入手してください。
Q.里帰り先で予防接種を受けたいのですがどうすればいいですか?
A.枚方市取扱医療機関以外で予防接種を受けたい場合は、事前に予防接種実施依頼書発行手続きをしていただく必要があります。事前の手続きがなければ定期接種の扱いとならず、実費となりますのでご注意ください。詳細はこちら。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (予防接種係直通)電話: 072-841-1429
ファックス: 072-845-0685
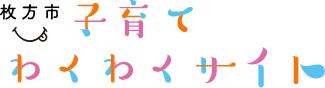
 ページ番号検索の使い方
ページ番号検索の使い方