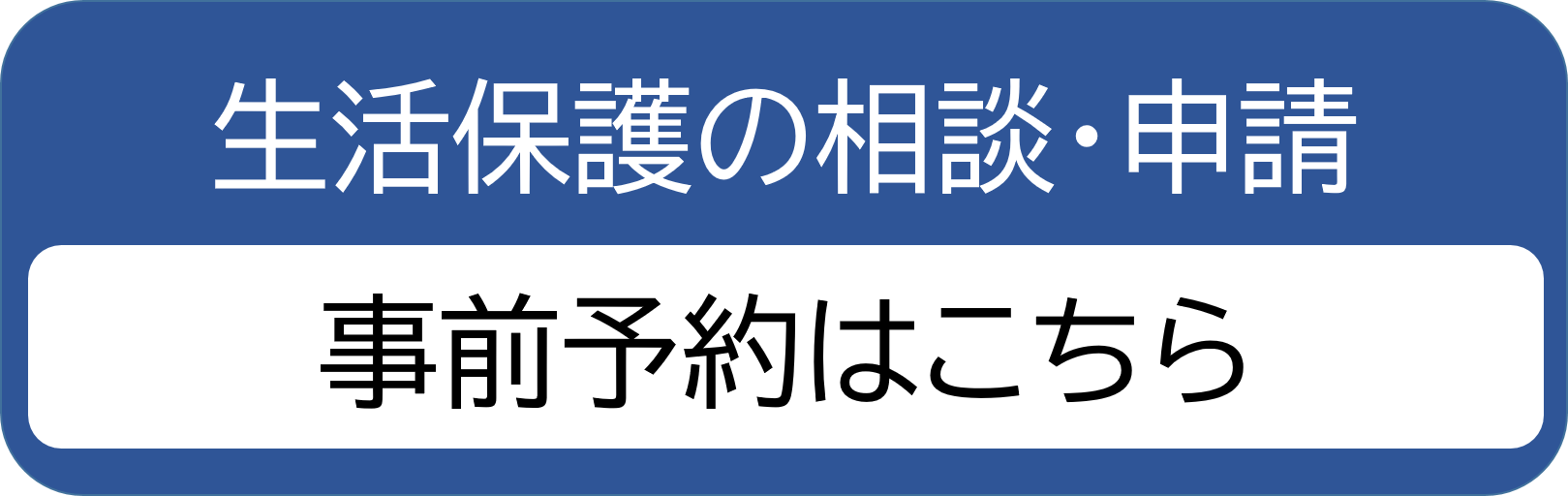生活保護の申請について
- [公開日:2026年2月3日]
- [更新日:2026年2月3日]
- ページ番号:32300
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生活保護を受けるには
生活保護を受けようとする方々の、個々の実情にあわせた相談・助言を行い、申請意思を確認したうえで、申請を受け付けています。
生活保護の申請は、国民の権利であり、申請権は保護を受けようとする本人、扶養義務者、同居の親族にあります。
生活保護は原則世帯単位で行い、申請前にその利用し得る資産や、能力の活用が要件として定められています。
また、入院・施設入所など、特別な事情により来所が困難な場合は、生活福祉課までご相談ください。
生活保護を受ける前に
生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるように努める必要があります。
1.働ける人は能力に応じて働いてください。
2.土地・家屋・預貯金・生命保険・損害保険等は、生活のために活用してください。
3.親・子・兄弟等の援助を受けるよう努力してください。
4.年金・手当のほかの法律によって受けられるものは、全て給付を受けてください。
5.そのほか、生活に役立つものがあれば、全て活用してください。
申請にあたってご用意いただきたいもの(例)
生活保護のご相談・申請にあたって、下記のものをご用意いただけると、手続きがスムーズにすすめられますが、個別に事情をお聞きしたうえで必要な書類についてはご説明しますので、申請時に確認することができない書類があっても申請することはできます。
・預貯金の通帳(最新の状態に記帳済みのもの)
・生命保険や損害保険の証書
・証券
・車検証
・年金手帳または年金証書と振込(改定)通知書
・給与明細書(直近3か月のもの)
・児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書
・児童手当の通知書
・雇用保険受給者証
・傷病手当の振込み通知書
・賃貸住宅の場合、賃貸借契約書や家賃の証明及び家賃領収書
・持ち家の場合は、不動産登記簿謄本と固定資産税の通知等
・障害者手帳等
・健康保険被保険者証、介護保険証(認定証等も)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカード(個人番号カード)によりマイナンバー(個人番号)を確認することができた場合は、一部書類の提出を省略できることがあります。
生活保護の決定
調査の結果、保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を、受けられない場合には、保護却下通知書を14日以内にお送りします。
ただし、調査に日時を要する場合は、30日までのびることがありますので、お早めにご相談ください。
保護のてびき
てびきには、生活保護を受けようとする人のために、手続きの方法等が書いてあります。
生活保護のてびき
生活保護の相談にかかわるQ&A
Q1.借金がありますが、生活保護は受けられますか。
A1.借金があることで生活保護を受けられないことはありません。しかしながら、生活保護は最低限度の生活を保障するという基本理念の趣旨からも、保護開始決定後に支給される保護費を借金の返済に充てることは望ましくありませんので、個別に法テラス等に相談して、任意整理や自己破産等で借金を整理する必要があります。
Q2.同居人がいますが、自分だけで生活保護を受けられますか。
A2.生活保護は生計が同じである同居人がいる場合、同じ世帯として考えます。そのため、原則自分だけで生活保護を受けることはできません。
Q3.持ち家ですが、生活保護は受けられますか。
A3.個別の状況に応じて、保有を認めることがあります。ただし、資産価値が大きい場合やローンがある場合は、原則認められません。詳細については相談時にたずねてください。
Q.4.自動車を持っていますが、生活保護は受けられますか。
A4.自動車や総排気量が125ccを超えるオートバイの保有や使用は、原則として認められていません。但し、障害者の方が通院のため使用せざるを得ない等やむを得ない場合について、審査のうえ保有や使用を認めることもありますので申し出てください。
原付バイクの保有や使用については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、要件を満たす場合は保有や使用を認めることもありますので、申し出てください。
Q5.働いているのですが、生活保護を受けられますか。
A5.働いていても生活保護は受けられます。ただし、収入がある場合、働いて得た収入も含め、世帯の全収入と最低生活費を比較し、収入が最低生活費より少ない場合はその差額分が支給されます。
詳細については相談時にたずねてください。
※最低生活費とは国が世帯の状況(世帯員数や障害の有無等)に応じて、1か月に必要な生活費として定めている金額です。
※働いて得た収入(給料・ボーナス等の臨時的収入)を申告すると、必要経費(交通費・社会保険料等)の控除だけではなく、基礎控除等の控除を受けられます。また、未成年者(特に高校生)の場合は、基礎控除にあわせて未成年者控除や大学等へ進学する場合の進学費用が収入額から除外される制度もあります。
Q6.生活保護を受けた場合、医療費はどうなりますか。
A6.生活保護の受給が決まれば、生活保護による医療扶助で医療費の全額を賄うことなります。社会保険に加入されている方は、社会保険の加入は継続し、自己負担分のみ全額医療扶助で賄われます。なお、保険外の診療や差額ベッド代等は原則として扶助の対象となりません。
Q7.仕事が見つからず困っています。生活保護で就労の支援は受けられますか。
A7.生活保護制度では、生活保護受給者で働くことができる方は、稼働能力を活かして働くことで自立を目指すことが求められています。枚方市では生活保護受給者で就労が可能な方たちが就職し、職場で定着することによる自立を目的として、専門の支援員が就労支援を行っています。
Q8.就労支援の内容を教えてください。
A8.枚方市では就労支援の対象者に対して次の支援を行っています。
(1)カウンセリング
就労支援員が対象者との面談を通じて就労への課題を相互に確認し、適職を選択するための手助けや、強みの発見と弱みの補強等の職業相談を行います。
(2)就労に向けた助言・指導
履歴書の書き方や面接等のトレーニング、対象者の適性・能力・条件に合った求人情報の提供、ハローワークや関係機関との連携による支援も行います。
(3)不採用時の対応
不採用であった場合、原因の検証・解決方法の検討を行います。
(4)就職決定後について
就職決定後は一定期間、対象者に連絡をとり、近況の確認・職場での問題や悩みに対する助言を行い、職場定着を目指します。
相談窓口について
生活福祉課では、その方の世帯の状況に応じて相談窓口を設けています。
自身がどの係に該当するか判断にお困りの場合は、どちらの窓口でもご相談をお受けしますので、まずはご来所ください。
〇生活福祉課 自立支援第一係・第二係
・単身世帯で65歳未満の方
・複数世帯で65歳未満の方が一人でもいる世帯の方
〇生活福祉課 高齢支援第一係・第二係
・単身世帯で65歳以上の方
・複数世帯で世帯員が65歳以上のみの方
相談・申請の事前予約について
令和6年9月17日(火)から生活保護の相談・申請の事前予約を開始しました。
希望日の2日前(閉庁日を含みません)までに予約されると、当日お待ちいただくことなく相談することができます。
〈例:令和6年9月20日(金)を希望→9月18日(水)までに予約、令和6年9月30日(月)を希望→9月26日(木)までに予約〉
事前予約していなくても、開庁時間内に直接窓口へお越しいただければ相談・申請ができます。
・予約は各日、午前と午後の合計2枠です(先着順)。ご希望の時間帯での予約が受け付けられない場合もありますので、予めご了承ください。
・予約された日時にお越しになられなかった場合、予約時間の15分経過後に自動キャンセルとなります。予約キャンセルとなっても開庁時間内に直接窓口へお越しいただければ、相談・申請を行うことができます。
問い合わせ先
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課
自立支援第一係・第二係 TEL:072-841-1452
高齢支援第一係・第二係 TEL:072-841-1454
健康・総合支援係(医療・介護)TEL :072-841-1546
健康・総合支援係(総務)TEL :072-841-1453
FAX:072-841-4123
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課
電話: 072-841-1452
ファックス: 072-841-4123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
 ページ番号検索の使い方
ページ番号検索の使い方
 ホーム
ホーム